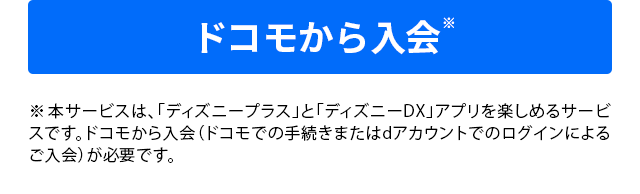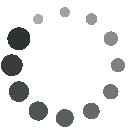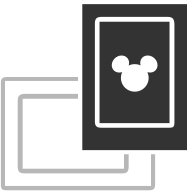『アナと雪の女王』(2014)の大事な登場キャラクターのひとつである"雪"。まるで命を宿したかのような臨場感ある雪の効果には、物理学を利用した、"マッターホルン"と呼ばれる独自シミュレーターが使われました。その開発秘話を同技術が使われたシーンとともに振り返ります。
マッターホルンとは?
マッターホルンは、ディズニー・アニメーション独自のシミュレーターの1つ。『アナと雪の女王』の雪を描くために開発されました。シミュレーターとは、雪などの描写の物理方程式を解くプログラムのこと。ディズニーのソフトウェア・エンジニアたちと、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の数学准教授のジョセフ・テラン、同校の博士課程修了学者であるクレイグ・シュローダーとの学術的コラボレーションによって生まれ、最近では、泥、泡、砂などの材料もシミュレートできる、より高度なモデルへとアップグレードされています

マッターホルンの開発は、それまで描くことの難しかった重厚感のある雪や、雪のかたまり同士がくっつく様子、キャラクターと戯れることにより起こる反応など、様々な雪の演出を可能にしました。
マッターホルンの技術が使われたいろいろなタイプの雪(3回繰り返します)
ドロリとした雪(soupy)→降りたての雪(freshy)→ふつうの雪(normaly)→ねばついた雪(stickyy)→ぼてっとした雪(chunky)→湿った雪(wet)→雪の塊(solidy)
同じ雪の運動でも、状況が異なるとどう反応するかのシミュレーションを何種類も用意することを可能にしたマッターホルン。もともと1~2つのシーンで使われる予定でしたが、最終的には43ものシーンで使われたそうです。
使われているのはどのシーン?
映画内のどのシーンにマッターホルンの技術が採用されたのでしょうか?象徴的なのは、王国を飛び出したエルサを探しに行ったアナが落馬した後のシーン。アナは頭上の木の枝につかまって起き上がろうとしますが、しなった枝がスリングショット(パチンコ)のように上空に雪を跳ね飛ばし、大きな雪の塊がアナの上に落ちます。ここでは、雪の塊の下の物体(木の枝)を運動学的に動かすと同時に、雪のシミュレーションを組み合わせ、リアルな落雪を作り上げることに成功しました。
雪男マシュマロウに追い払われたアナたちが落下した後のシーンもそうです。雪の中に腰まで埋まったアナをクリストフが引き上げに行く際、クリストフが歩くたびに地面の雪が小さく砕かれ、ランダムに積み重なります。アナが引き上げられる瞬間も、周りの雪がくっついてはポロポロと崩れる様子が分かります。

マッターホルン技術の使用前後を比較した動画
もうひとつの例は、アナとクリストフが、森の中でオオカミたちに追われるシーンで、雪上に残るソリの痕跡もマッターホルンの技術によるもの。どれも意識していないと見逃してしまうほど自然に描かれています。こうしたディテールを積み重ねて、リアルに感じられる雪景色が作られたわけです。
ちなみにこのマッターホルンは、本作において雪だけでなく、ある泥の描写にも応用されています。どのシーンか分かるでしょうか?ヒントは、アナとクリストフを結びつけようとするトロールたちのシーンです。ぜひ探してみてください。
『アナと雪の女王』を何度も観た方でも、雪の動きに注目して観ると、また新たな発見がありそうですね。

 Disney+(ディズニープラス)は、ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービスです。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナルジオグラフィックの名作・話題作に加え、多様なコンテンツを提供するブランド、スターでは、『SHOGUN 将軍』をはじめとした作品を手掛けるFXや20世紀スタジオなど世界最高峰のクリエイティブチームが制作する作品や、日本や韓国で絶賛されたドラマやアニメなどを多数配信しています。
Disney+(ディズニープラス)は、ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービスです。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナルジオグラフィックの名作・話題作に加え、多様なコンテンツを提供するブランド、スターでは、『SHOGUN 将軍』をはじめとした作品を手掛けるFXや20世紀スタジオなど世界最高峰のクリエイティブチームが制作する作品や、日本や韓国で絶賛されたドラマやアニメなどを多数配信しています。ドコモから入会をいただくと、お得な特典やもっとディズニープラスを楽しめる情報、コンテンツが満載のディズニーDXもセットでお楽しみいただけます。
毎日が楽しめるコンテンツが充実!「ディズニーDX」アプリ
 「ディズニーDX」アプリは、Disney+(ディズニープラス)にドコモから入会いただくことでご利用いただけます。お得な特典や、ディズニープラスをもっと楽しむための豊富なコンテンツがお楽しみいただけるアプリです。
「ディズニーDX」アプリは、Disney+(ディズニープラス)にドコモから入会いただくことでご利用いただけます。お得な特典や、ディズニープラスをもっと楽しむための豊富なコンテンツがお楽しみいただけるアプリです。