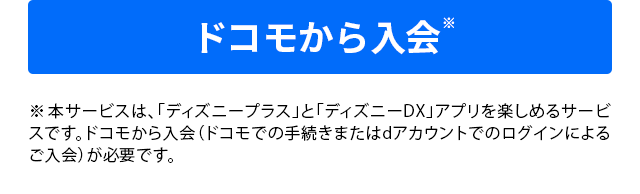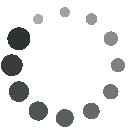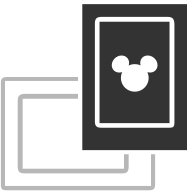自身の記憶や家族が放つヒントを作品に活かすことで知られるピート・ドクター監督。『ソウルフル・ワールド』(2020)は、ピート・ドクター監督が、子どもが誕生した際に感じた"個性はどうやって備わるんだろう?"という疑問から生み出されたのだそうです。そんなピート・ドクター監督が原案や脚本、監督を手がけた名作5本をご紹介します。
『トイ・ストーリー』(1995)
大学卒業後、21歳からピクサーで働き始めたピート・ドクターが、ジョン・ラセターやアンドリュー・スタントンらと原案を担当した『トイ・ストーリー』。ピート・ドクターは、バズ・ライトイヤーのキャラクターを担当。机の上に置いた鏡で、時々自分の顔を見ながら作り上げていったバズ・ライトイヤーには共鳴する部分があったそう。
おもちゃ同士、おもちゃと人間など、さまざまな組み合わせで胸に迫る物語が描かれる本作。なかでも、アンディやおもちゃの仲間が新参者のバズに関心を寄せることにウッディが傷つく場面と、自信満々だったバズが実は大量生産されたおもちゃの1つだと気づいて落ち込む場面は、身につまされますよね。
ウッディのキャラクターを担当したのはアンドリュー・スタントン。ウッディとバズのキャラクターには、アンドリュー・スタントンとピート・ドクターの一部が様々に反映されていそうですね。
『モンスターズ・インク』(2001)
ピート・ドクターが長編監督デビューを果たしたのは、『モンスターズ・インク』です。本作は、『トイ・ストーリー』を作っているときに、人間が見ていないとおもちゃは自由に動き回っていると信じていた人が多かったことにヒントを得たのだそう。そんなふうに子どもの頃に信じていたことを思い浮かべたとき、ピート・ドクター監督はクローゼットの中に隠れているとされたモンスターの存在を思い出したのだそうです。
業績トップになることにしか興味のなかったマイクとサリーが、子猫のように無防備で天真爛漫(てんしんらんまん)な人間の女の子ブーを守ろうとして振り回される姿は大いに笑えます。同時にピート・ドクター監督は、この出会いが彼らをある種の父親へと導いていると語っています。ちょうど子育ての真中だったピート・ドクター監督の実感も反映されているのかもしれませんね。
『ウォーリー』(2008)
ピート・ドクターがコンセプトを考え、アンドリュー・スタントンに企画をバトンタッチしたのが『ウォーリー』です。当初、ピート・ドクターが考えた話は、エイリアンの家族が夏休みのバケーションに訪れると、リゾートのはずがゴミの惑星で、そこに住む孤独なロボットに脅かされるというものだったようです。
ゴミだらけの惑星に残された孤独なロボットというアイデアは、アンドリュー・スタントンの心を捉え、この物語をラブストーリーにできると考えた彼が監督となり、完成しました。映画が完成するまでには、ピート・ドクターが昼休み、ジョン・ラセターとジョー・ランフトに最初のアイデアを語ってから14年もの年月が経っていました。
『カールじいさんの空飛ぶ家』(2009)
ピート・ドクターが共同脚本と監督を担当した『カールじいさんの空飛ぶ家』。カールじいさんの妻の名前は、ピート・ドクター監督の娘エリーさんにちなんでつけられ、エリーさんは若き日のエリーの声も担当しています。
部屋でひとり、思い出のアルバムをめくりながら、しんみりしていたカールじいさんが、最後のページにエリーの手書きメッセージを見つけるシーンは、過去を思う切なさと、未来に向けた希望が入り混じる優しい名場面ですね。
『インサイド・ヘッド』(2015)
ピート・ドクターが共同脚本と監督を手がけた『インサイド・ヘッド』。主人公の11歳の少女ライリーは、ピート・ドクター監督の娘エリーさんにインスピレーションを受けて生まれたキャラクターなのだそう。活発だったエリーさんが、11歳頃から内気になったように感じられたピート・ドクター監督が、子どもの脳内で何が起きているのかを考え始めたことから、同作がスタートしたといいます。
そんなドクターの父親目線が感じられるのが、感情の起伏に戸惑いながら強がってきたライリーが初めて、パパとママの前で<カナシミ>を吐露するシーン。健気なライリーと、子育てに葛藤してきた両親の想いが重なるとき、観ている私たちも、すべての感情を愛しく思える気がしますよね。
*本記事の作品公開年はアメリカ公開の年を記載しています
ピート・ドクター監督最新作
『ソウルフル・ワールド』のご視聴はこちらから
 Disney+(ディズニープラス)は、ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービスです。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナルジオグラフィックの名作・話題作に加え、多様なコンテンツを提供するブランド、スターでは、『SHOGUN 将軍』をはじめとした作品を手掛けるFXや20世紀スタジオなど世界最高峰のクリエイティブチームが制作する作品や、日本や韓国で絶賛されたドラマやアニメなどを多数配信しています。
Disney+(ディズニープラス)は、ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービスです。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナルジオグラフィックの名作・話題作に加え、多様なコンテンツを提供するブランド、スターでは、『SHOGUN 将軍』をはじめとした作品を手掛けるFXや20世紀スタジオなど世界最高峰のクリエイティブチームが制作する作品や、日本や韓国で絶賛されたドラマやアニメなどを多数配信しています。ドコモから入会をいただくと、お得な特典やもっとディズニープラスを楽しめる情報、コンテンツが満載のディズニーDXもセットでお楽しみいただけます。
毎日が楽しめるコンテンツが充実!「ディズニーDX」アプリ
 「ディズニーDX」アプリは、Disney+(ディズニープラス)にドコモから入会いただくことでご利用いただけます。お得な特典や、ディズニープラスをもっと楽しむための豊富なコンテンツがお楽しみいただけるアプリです。
「ディズニーDX」アプリは、Disney+(ディズニープラス)にドコモから入会いただくことでご利用いただけます。お得な特典や、ディズニープラスをもっと楽しむための豊富なコンテンツがお楽しみいただけるアプリです。