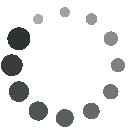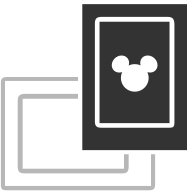ディズニーパークには、ディズニー作品をベースにしたアトラクションがたくさんあります。「空飛ぶダンボ」、「ピノキオの冒険旅行」、「ピーターパン空の旅」、「白雪姫と七人のこびと」などです。
また、反対に、ディズニーパークのアトラクションからストーリーを生み出し、作られた映画があるのはご存知ですか?なかでも絶大な人気を誇るのは、「カリブの海賊」を映画化した『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズでしょう。

海賊は紀元前から存在していた!
海賊は、はるか昔紀元前から、地中海などに存在していたと記録されています。8~11世紀にヨーロッパ沿岸部を侵略した北欧のヴァイキングから、現在タンカーなどを襲う者たちまで、広く海賊と呼ばれていますが、海賊と聞いて私たちが思い浮かべるのは、なんといっても『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズに出てくる、17~19世紀にかけてカリブ海を暴れまわった海賊たちではないでしょうか。でもなぜ、「海賊といえばカリブ!」と多くの人がイメージするのでしょう。
新大陸の発見とヨーロッパ諸国の対立が海賊を増長させた
アメリカ大陸が発見されたのち、スペインは新大陸の植民地化を進め、この地からもたらされた金銀の財宝を、船でヨーロッパに運びました。
そこに目を付けたのが海賊たち。スペインの貿易航路に当たるカリブ海で、輸送船や商船を襲えば、一度に莫大な富を手に入れることができます。新大陸にやってきた貧しい労働者や職を失った軍人、乗っていた商船が襲われてそのまま略奪者の仲間になった水夫など、多くの人が海賊に身を投じ、一大海賊社会を築いていきました。

『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズにも登場するジャマイカ島のポート・ロイヤルやトルトゥーガ島は、実際に海賊たちの活動拠点となっていたところです。
スペインの船を狙う海賊行為は、スペインと対立関係にあり、同様に新大陸で植民地獲得を狙うイギリス、フランス、オランダ各国にとっても好都合。各国が海賊に、敵国船拿捕許可状を与え、国家公認の合法な海賊船、私掠船が誕生しました。捕獲品は海賊と分配し、国はここから莫大な予算を獲得していたのです。
シリーズ第2作『デッドマンズ・チェスト』(2006)でも、絶大な権力を持つ東インド会社のベケット卿がジャック・スパロウに敵国船拿捕許可状を与える代わりに、不思議な力を持つ"北を指さないコンパス"を手に入れようとします。
海賊物語に大きな影響を与えた「宝島」
『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズの背景には、こうした史実だけではなく、文学作品や映画、オペラまで、さまざまなエッセンスがちりばめられています。
ロバート・ルイス・スティーヴンソンの冒険小説「宝島」と、ジェームズ・マシュー・バリーの戯曲&小説「ピーター・パン」は、豪快でロマンあふれる海賊のイメージを定着させたといわれています(2作ともディズニーで映画化されていますね)。
シリーズ第2作のタイトル『デッドマンズ・チェスト』も、実は「宝島」の一節からとられているんです。
ジャック・スパロウの右腕ギブス(もとは海軍の航海士で、いまはなぜか海賊の仲間)が、船上でラムを飲みながら歌う、「"死者の宝箱"って島に 取り残された15人の男 ヨーホーホー ラムをラッパ飲み」。これは小説「宝島」の冒頭で、かつて海賊だった男が口ずさんでいる歌です。
この"死者の宝箱(デッドマンズ・チェスト)"こそ、あのデイヴィ・ジョーンズの心臓の入った箱のこと。そして映画のアイデアのもとになっているのです。この歌、なんとスウェーデンの児童文学「長くつ下のピッピ」シリーズにも登場します。ピッピは海賊ごっこをする時、これを歌っています。「宝島」がいかに世界中で愛されているのか、わかりますね。
悪霊伝説からオペラまでさまざまなオマージュ
2作目、3作目に登場するフライング・ダッチマン号の船長デイヴィ・ジョーンズ。顔はタコの足のような髭(?)で覆われ、右手はタコ足、左手はカニの爪というインパクト絶大の姿をしています。

もともと"デイヴィ・ジョーンズ"とは、古くから船乗りたちに恐れられていた海の悪霊の名前。名前の由来には諸説ありますが、船が沈没したり、水死者が出たりすることを、彼らは「デイヴィ・ジョーンズの監獄(Davy Jones' Locker)に送られる」と表現していました。生きることも死ぬこともできずにジョーンズのもとで働かされている海賊たちにとって、フライング・ダッチマン号はまさに監獄だったに違いありません。
このフライング・ダッチマン号の物語にもベースがあります。神を冒涜したために罰を受け、この世とあの世の間を永遠にさまよい続けることになったオランダ人船長の船が、喜望峰の近海で目撃されるという幽霊船フライング・ダッチマンの伝説です。
この伝説をもとに、ワーグナーが作曲したオペラが「さまよえるオランダ人」です。オペラの物語では、オランダ人船長は7年に一度だけ陸にあがることを許されており、彼に永遠の愛を捧げる女性が現れれば呪いが解ける、とされています。
映画のデイヴィ・ジョーンズは、10年に一度上陸を許されており、愛する海の女神カリプソとの逢瀬を心待ちにしていた、というあたりは、ワーグナーのオペラへのオマージュでもあるのでしょう。

シリーズ第4作『生命の泉』(2011)には、実在した海賊、エドワード・ティーチが登場します。名前よりも"黒ひげ"の愛称で知られるティーチは、大男で極悪非道、カリブ海最強の海賊として恐れられました。
髪やヒゲを編んでリボンやビーズで飾っていたと伝えられていますが、そのファッションはジャック・スパロウに受け継がれているのかもしれません。黒ひげは本作では、ジャック・スパロウのかつての恋人、今は女盗賊アンジェリカの父親という設定になっています。

見つけると楽しいアトラクションとの共通点
もちろん、オリジナルのアトラクション「カリブの海賊」にインスパイアされたシーンも、シリーズのところどころに登場します。『呪われた海賊たち』の冒頭、幼き日のエリザベスが船の舳先で歌っているのは、アトラクション内で海賊たちが陽気に歌っている「ヨーホー ヨーホー(海賊の暮らし)」。
第5作『最後の海賊』(2017)の原題、「Dead Men Tell No Tales(死人に口なし)」は、アトラクションで海賊の世界に入り込む前にゲストが受ける警告の文句から取られています。『最後の海賊』では、ジャック・スパロウによって魔の三角海域に沈められたスペイン戦艦サイレント・メアリー号のサラザール艦長のゴーストが、このセリフをつぶやきます。
ほかにも映画には、骸骨姿のバルボッサが飲んだワインが肋骨の間を通っていくのが見えたり、牢屋に入れられた海賊たちが牢の鍵をくわえた犬をおびき寄せようとしていたり、港町で女性たちを追いまわす海賊たちがいるかと思えば、逆にほうきを持った女性に追いかけられる海賊がいたり、酔っ払いが豚小屋で寝ていたり……「カリブの海賊」ファンなら思わず「あ、あれ!」と言ってしまいそうなシーンがいっぱい。
映画の公開後、ディズニーランドのアトラクションはリニューアルされ、ジャック・スパロウとヘンリー・バルボッサ、デイヴィ・ジョーンズが新たに登場人物に加わりました。映画もアトラクションも、それぞれの背景を知っていると、さらに楽しめますね。